文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、鷹羽康博
梁瀬 薫(やなせ・かおる)さん|アート・プロデューサー/アート・ジャーナリスト
東京都小金井市出身。1979年3月、武蔵野女子学院高等学校(現 武蔵野大学高等学校)を卒業。1986年にニューヨーク近代美術館(MoMA)のプロジェクトのアシスタントとして採用され渡米。そのままニューヨークを拠点にして、コンテンポラリーアートを軸に、アーティストの紹介、展覧会の企画とプロデュース、展覧会のカタログ執筆や翻訳など、幅広く活動を続けている。国際美術評論家連盟米国支部の評議員。2008年からは山梨県にある中村キース・ヘリング美術館の顧問を務める。共著に『マイ・アート―コレクターの現代美術史』(スカイドア)がある。
物事をやり抜く力はトラックフィールドで培われた
 陸上部での整列写真。前列右から2人目
陸上部での整列写真。前列右から2人目「まだ走れる、まだ走れる」
陸上部の練習がラストスパートに入り、武蔵野女子学院高等学校(現 武蔵野大学高等学校)の校庭に北岡和彦先生や則末忠衛先生の声が響き渡る。部員で中距離走者の梁瀬薫さんは「もう走れない」と泣きながら、それでもなんとか走り抜いた。
アメリカのニューヨークを拠点にアート・プロデューサーやアート・ジャーナリストとしての活動を続けてきた梁瀬さんは「まだ走れる、まだ走れる」という言葉をいまだによく覚えている。アートの世界に足を踏み入れてから40年近く、物事をやり抜く力はトラックフィールドで培われた。
「あとちょっとで倒れる、自分は死ぬんじゃないかというぐらい息切れしているのに『まだ走れる、まだ走れる』と優しく、さらりと言われて、そうすると『走れるかも』と思わされて、最下位でしたが、走り切れたんです。そのときの達成感ほど感動したことはありません。あのときに鍛えられた諦めない心や何かをやり遂げる力は今でも生きていると思います」
最前列左から2人目。自由さを満喫した
懐かしそうに卒業アルバムをめくる
公立中学校から入学した武蔵野女子学院高等学校で好きだったのは解放感だという。「やりなさい」と言われたことは一度もないけれど、小さなころから親の敷いたレールを歩んでいるような感覚があった。花道や書道、あるいはピアノなどさまざまな習い事を続け、母が嗜んでいた能楽堂も記憶に残る。学級委員も務め、成績も悪くない自分は、どこか親や近所に住む親戚の顔色をうかがっていた気がする。少しだけ窮屈だった。それが、武蔵野女子学院高等学校で一転した。梁瀬さんは笑顔を浮かべる。
「まずキャンパスが広くて、雰囲気も穏やかで、ものすごくのびやかに過ごせたんです。守衛のおじさんとすごく仲良くなったのも忘れられませんね。『8時ぐらいに来ればいいよ』と言ってもらって、みんなが帰ったあとの夜、実際に行くと明かりをつけてくれて、一人で絵を描いたり、一人で広い校庭を走ったりして。自分らしくあっていいという自由さを満喫できた3年間でした」
武蔵野キャンパスで育んだやり切る力と自分らしさに身を委ねる姿勢は、アートを見極めたり、発信したりする人生に大きく役立ってきた。「美術なんかやっていてもお金にならない、牛乳も買えなかったときもありました」という苦しい時期を経験しながらもしぶとく続けてこられたのは、アートの世界こそが自分の居場所だと感じているからだ。
アーティストとしての行き詰まりが人生に変化をもたらす
アートの仕事で頻繁に帰国している
絵を描くのは小さなころから好きだった。高校時代の文化祭ではクラスで1950年代や1960年代のツイストダンスなどを披露する催しを開くことになり、自身は美術担当になった。当時のアートスタイルを模して教室を飾ると、周囲から称賛を受け、すっかりその気になった。曰く「自分は天才」だと信じ、卒業後は一浪の末、美術大学に進学した。
1986年、転機が訪れる。美大を卒業してからほどなく、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のプロジェクトのアシスタントとして採用され、 アメリカに渡った。約一年にわたってドイツ人アーティストの補佐をしたり、そのままアメリカに残ってニューヨークで現在進行形で動くアートシーンに刺激を受けたりする一方、高い鼻はへし折られた。まず、英語でのコミュニケーションの壁に突き当たった。ニューヨークでは自分を主張できないと取り残されるし、人と同じスタイルでは無視される。その行き詰まりが人生に変化をもたらした。梁瀬さんは振り返る。
「それまでは『自分は天才』だと思っていたんですが、世界を見たら全くそんなことはなくて。当時のニューヨークにいるアーティストたちはみんなやっぱりすごい才能を持っているんですよね。そして社会の不平等さや政治に対して声を上げているような強烈な作品を目の当たりにしたんです。ですから、絵を描くのはもちろん好きですけど、私は素晴らしいアートの力を伝える役割を選ぶことにしました」
その決意とともに、アート関連の定期刊行物を発行する美術出版社のニューヨーク支部を立ち上げ海外情報事業を担当することになった。
 1986年からニューヨークを拠点に活動
1986年からニューヨークを拠点に活動ただし、新しいアートを発見し、発信する仕事は決して楽ではなかった。まだインターネットのない時代にあって、これから世に出ていくであろうアーティストたちの多くは夜な夜なクラブに集う。原石たちに会うべく、自身も足繁くクラブに通った。朝帰りをして2時間だけ寝て、美術出版社で働いたあと、日本の新聞社のニューヨーク支局に移動し、夜にアメリカやニューヨークのアートシーンを紹介する記事を書き、またクラブに足を運ぶ。疲労困憊した週末は文字どおり泥のように眠った。
身を粉にしても働き続けられたのは、自分が心を揺さぶられたアートを広く知らせたかったから、そして何より「まだ走れる、まだ走れる」という言葉に背中を押され、実際に頑張れた実体験があったからにほかならない。
幅広く美術に関わってきた自分の仕事は“アートの翻訳者”
日本から飛び立って40年足らず、ニューヨークの街にはどこか武蔵野女子学院高等学校と似た雰囲気があるという。それぞれの個性を認め、多様性を受け入れる空気感は、居心地の良かった3年間の環境に通じる部分がある。つまり、自分が自分らしくいられる。だから、ニューヨークに住み続けている。
 中村キース・へリング美術館の顧問を務める。エチオピアのアーティスト、ワセニ・ウォルケ・コスロフ氏のワークショップで
中村キース・へリング美術館の顧問を務める。エチオピアのアーティスト、ワセニ・ウォルケ・コスロフ氏のワークショップでアート・プロデューサーやアート・ジャーナリストとしては、歴史に名を残す芸術家とも出会ってきた。アンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンスタイン、ジャン=ミシェル・バスキア、キース・へリングなど1980年代のアートシーンを代表するアーティストから、草間彌生、オノ・ヨーコにインタビューをしたこともある。トニー・アウスラーやエイミー・カトラーといった作家がほとんど無名の状態から成功の階段を駆け上がっていく過程も目にしてきた。そうした経験を評価され、2008年からは山梨県にある中村キース・ヘリング美術館の顧問を務めている。梁瀬さんは、長く、幅広く美術に関わってきた自分の役割は“アートの翻訳者”だと話す。
「私は自分のことをハブだと思っているんですね。作家が絵画なり彫刻なりの作品を通して言いたいことを言葉に直してあげて、見る人たちに伝える中間地点にいるイメージです。あるいは、作家が言っていることを英語でも日本語でも皆さんがわかりやすい表現で伝える、そういう作業が仕事なのかなというふうに考えています」
小さいころに花道や書道、あるいはピアノなどさまざまな習い事を通して興味の幅を広げた経験は、めぐりめぐってこれからの夢につながっている。“アートの翻訳者”だけで終わるつもりはない。やりたいことはいくつもある。梁瀬さんの目が輝く。
「アートの世界では新しい才能をどんどん発掘したいですし、若い人たちの展覧会をいろんなところで開催したいです。映画をつくりたいし、小説も書いてみたい。また絵を描きたい気持ちもありますし、大学院に行って美術史をもう一度学び直したいという思いもあります」
あのころ校庭で何度も聞いた「まだ走れる、まだ走れる」という言葉に後押しされるように、梁瀬さんの人生は挑戦的に続いていく。
「映画をつくりたいし、小説も書いてみたい。また絵を描きたい気持ちもあります」
関連リンク
※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。
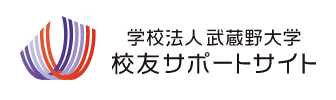











コメントをもっと見る