文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、小黒冴夏
工藤聖奈(くどう・せいな)さん|東京電力ホールディングス株式会社
東京都出身。2021年3月に武蔵野大学の工学部建築デザイン学科を卒業。2023年3月に武蔵野大学の大学院工学研究科建築デザイン専攻を修了。在学時はなるべく建築に関わる時間を増やしたい思いで、住宅展示場のアルバイトや、学内のスチューデント・アシスタントやティーチング・アシスタントのアルバイトをし、視野を広げられるよう海外からの高校留学生を支援する公益財団法人でのボランティアに励んだ。学生時代は友人や家族のつながりを通してイギリスやアメリカ、モルディブや韓国に滞在し、国外の建築から刺激を受けたうえ、日本とは異なる暮らし方や価値観にもふれた。
「ものをつくりながら考えた経験は武蔵野大学で学んだ財産」
 高校時代、フランク・ロイド・ライトの自邸兼事務所を見学
高校時代、フランク・ロイド・ライトの自邸兼事務所を見学小さいころ、新築一戸建てや分譲住宅のチラシを眺めるのが好きだった。印刷された間取りを見て、自分が住む家と比べて今とは違う暮らしを空想するのが楽しかった。企業の建築士として働く父の影響もあったと感じている。
中高一貫校に進学したあとも興味は変わらなかった。中学3年生のときには学問の対象として建築を掘り下げている。工藤聖奈さんは回想する。
「中学卒業論文という取り組みで建築をテーマにしたんです。特に機械に頼らず、太陽の熱や光、風や植物といった自然の力を活用する『パッシブデザイン』という設計手法に注目しました。参考文献を読んでパッシブデザインの定義やメリットについてまとめ、自宅をパッシブデザインにより近づけた設計図面も書きました」
チラシを見て楽しいなと思っていただけだったのが、「建築を学問として考えてみたい」に変わった。武蔵野大学で教える金政秀教授の論文を読んで、建築と環境の関係性への興味が深まった実感があった。高校時代には、当時、武蔵野大学の工学部建築デザイン学科で教壇に立っていた河津優司教授の模擬授業を受け、オランダの街並みの話などで盛り上がった。家族旅行でアメリカを訪れた際には、有名な建築家であるフランク・ロイド・ライトの自邸兼事務所を見学した。
 苦労して仕上げたHPシェルは実習棟のそばにある(取材当時)
苦労して仕上げたHPシェルは実習棟のそばにある(取材当時)2人の教授の存在も手伝い、武蔵野大学の工学部建築デザイン学科への進学を決める。入学直後からの3年間、薄い曲面板の「HPシェル」という構造物をつくったグループでのプロジェクトは忘れられない。工藤さんが明かす。
「鉄筋コンクリート造なんですけど、曲線の型枠を木材でどうつくるのか、接合部はどうするのか、型枠にのせるコンクリートの粘度は気候に合わせどうするのか、試行錯誤を重ねました。実際、制作している私たちも『いつ完成するんだろう?』と思っていましたが、私が3年生のときにようやく完成させられて、それはすごく達成感がありました。ただ座学を受けるだけじゃなくて、実際に手を動かしてものをつくりながら考えた経験は武蔵野大学で学んだ財産になっています」
地域に溶け込んだ建築がテーマの卒業設計は優秀作品賞に選出
 大学2年次の夏休みはアメリカの国立公園で過ごした
大学2年次の夏休みはアメリカの国立公園で過ごした2年次の夏休みには、視野を広げようとアメリカで1カ月半ほど過ごしている。小さなころから家族がホストファミリーとしてフィンランドやオーストリアなどから留学生を迎え入れたり、家族でアメリカやカナダに旅行に出かけたりしていて、世界が身近にあった。アメリカにはワークトラベルという学生を対象にした就業体験プログラムを利用して滞在し、モンタナ州のグレイシャー国立公園のロッジ風のホテルで住み込みで働いた。未熟な英語ながら世界から集まった同世代の仲間たちとコミュニケーションをとった1カ月半は自信につながった。
武蔵野キャンパスに目を戻せば、1年生から3年生までで思い出深いのは設計製図の講義だったという。住宅から始めて、大学のサテライトキャンパス、美術館や劇場などの作品をひたすら制作した。敷地や周辺地域の課題と特徴を見つけ、自分なりのコンセプトを設定し、実際に図面や模型、パソコンのデザインソフトを使いながら、コンセプトを育ててかたちにしていく過程は、一筋縄ではいかない。教授と対話を重ねながら設計を練り上げる時間は、間違いなく充実していた。
 卒業設計では千川上水に注目した
卒業設計では千川上水に注目した3年間で建築の基礎をたたき込んだあとは、卒業設計が待っていた。工藤さんは武蔵野キャンパスのそばに流れる千川上水に注目する。江戸時代から続く水の流れの周りに息吹を与えたかった。
「実際に千川上水のほとりを歩いていると、空き家が増えている感じがしたんですね。ですので、地域のコミュニティをつなぎ止められる建築をつくりたいなという発想から始めました。何度も千川上水のそばに足を運んで自然に寄り添うかたちを探り、地域の暮らしに溶け込んだ建築をテーマにして、美術館とアトリエ、展示室といった空間をもつアート施設を提案しました」
およそ9カ月かけて仕上げた「The Stream ―水とアートが流れる暮らし―」は卒業設計のなかで優秀作品賞に選ばれた。14カ所と敷地が分散していて、数が多いながらも各々がしっかり設計されている点が評価されたのだという。大学生活の締めくくりとして2キロメートルほど歩くことになる広がりを完成させた工藤さんは、一定の達成感を得ながら「ようやくスタートラインに立てたかな」と心を引き締めた。
卒業設計は優秀作品賞に選ばれた
手を動かしたものづくりが財産だという
修士設計の「Grove Dub - 小石川ハウス alley -」は参加型建築
 修士設計は文京区の路地につくった
修士設計は文京区の路地につくった4年生になる直前には、大学院へ進学しようと決めていた。設計製図を含む3年生までの講義でどうにか土台づくりを終えられたというのが率直な実感だった。「3年間の学びを終えて、やっとデザインって面白いかもしれないと思えたんです」と話す。
大学4年間の集大成となる卒業設計を終え、大学院の2年間でまた別のテーマに取り組む。新たな決意を持った工藤さんは1年目、参加型建築の研究に励んだ。実際に建築を使う人やコミュニティが建築設計やまちづくりに携わる事例と向き合う学びは、卒業設計の「地域に溶け込んだ建築」の延長線上にあった。
その研究をいかに修士設計に落とし込むか悩んでいたとき、大学院で師事する水谷俊博教授の建築設計事務所が東京都内にある築60年ほどの木造2階建て住居の一部をリノベーションしていた。研究室の活動に理解のある所有者と話し合いながら進めた住居の一部と敷地内の通路での実践を通して、修士設計のテーマである参加型建築設計やまちづくりについて知見を深めていった。
 参加型建築の修士設計はレイアウトを変えられる
参加型建築の修士設計はレイアウトを変えられる修士設計として完成させ、その後は後輩たちが引き継いでくれ、さらに発展させてくれる予定の「Grove Dub – 小石川ハウス alley -」はまさに参加型建築だ。工藤さんが解説する。
「周辺住民が集まる人数や目的に合わせて、シンプルな木のフレームのなかで、さまざまな高さに変えられる横材と天板により、平面のレイアウトを自由に変更できる小建築を設計し、実際に施工しました。天板は置く位置によって、たとえば椅子にもなるし、テーブルにもなるし、展示台にもなります。車が通ることのできない路地にあって、周辺に暮らす人たちが思い思いに平面のレイアウトを変える行為を通じて、住民同士がつながるきっかけとなり、まちづくりに参画する可能性を持つ空間をイメージしました」
かつて新築一戸建てや分譲住宅のチラシを眺めるのが好きだった少女は今、具体的な夢に向かって邁進している。
「直近の目標としてはまず1級建築士の資格を取りたいです。そして、自然や地域に寄り添った建築はもちろん、『建築する』という行為によって人と人、人とまちがつながるきっかけとなるような建築設計や空間づくりに関わっていきたい。そういった建築や空間が増えることで、多くの人の暮らしが豊かになっていくと考えています」
1級建築士の資格を取り、人と人、人とまちがつながるきっかけとなるような建築設計や空間づくりに関わっていきたい
※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。
関連リンク
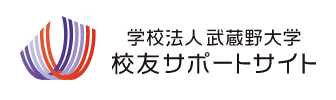











コメントをもっと見る