文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、小黒冴夏
粂田珠里(くめた・しゅり)さん|保健師
静岡県出身。2022年3月に武蔵野大学看護学部看護学科を卒業。在学中には看護師国家試験と保健師国家試験、さらには公務員試験に合格した。2022年4月から東京都内の保健センターで保健師を務める。大学時代に好きだった場所の一つは武蔵野キャンパスの図書館で、「歴史を感じさせる落ち着いた雰囲気が好きでした」と話す。趣味は旅行で、特に韓国をよく訪れる。ヨーロッパにもいつか行きたいという。
保健室の先生を憧れに、保健師をめざすことに
高校生のとき、保健師になりたいと思った。粂田珠里さんは思春期のころの記憶を手繰る。
「中学生のときに体調を崩したり、心が弱ってしまったりして、保健室に行くことが多かったのですが、そのときの保健室の先生がいつも優しく私の話を聞いてくださいました。その先生のように自分もなりたいと思ったのが、最初のきっかけです。話しやすくて、頼りたくなる存在だったので、すごく憧れがありました」
高校生のころ、多様な人生に関われる職業だとわかり、保健師をめざすことに決めた
保健室の先生は親以外で初めて心を許せる大人だった。最初はだから、「保健室の先生になりたい」と考えていたという。けれども、進路を真剣に検討し始めた高校2年生のころ、さらに視野が広がった。母が保健師という存在を教えてくれた。
自分で保健師の仕事を調べてみると、地域の赤ん坊からお年寄りまで、いろいろな人の心や健康の相談に乗ることができて、多様な人生に関われる職業だとわかり、保健師をめざすことに決めた。保健室の先生のような包容力を持って、さまざまな人の話に耳を傾けたいと考えた。「保健師は病気になっている人や心が弱ってしまっている人だけではなく、地域に根ざしながら予防的な段階から介入できるのがいいなと思ったんです」と明かす。
国公立の大学も受けたけれど、本命は武蔵野大学だった。高校3年生のとき、オープンキャンパスで武蔵野キャンパスを訪れ、東京なのに緑が豊かで落ち着く空間だとすぐに気に入った。東京の総合大学で、保健師課程のある看護学部で、と条件を絞っていくと、やはり武蔵野大学の看護学部に進む選択が最適のように思えた。
武蔵野キャンパスの銀杏並木は今でも印象に残っているという
武蔵野大学の看護学部看護学科の受験に合格し、2018年4月に大学生活がスタートする。ほどなく、武蔵野大学に入学してよかったと実感した。粂田さんは話す。
「入学前から楽しみにしていた基礎フィールド・スタディーズは、学部の垣根を超えたグループでの学びで、私は台湾を訪れ数日間を過ごしました。その取り組みで初めて知り合う人たちと初めての場所をめぐる時間はとても刺激的でしたね。それから、仏教の授業も新鮮でした。相手の幸せを願う心、他者の苦しみを理解して、その苦しみを和らげることを願う心が仏教の教えであって、そうした姿勢は看護にも共通していると感じました」
実習先が多く、さまざまな環境や治療方針にふれられた
「病理学」「薬理学」「公衆衛生学」「栄養学」「看護学概論」「看護倫理」……1年次は必修の講義で看護の基礎をたたき込んだ。2年次に本格的な実習が始まり、いくつかの病院で実践的な学びを深めていく。実習先が多い点は、さまざまな環境や治療方針にふれられる意味でメリットが多いと感じたという。
夢を見据えた大学生活は掛け値なしに充実していた。粂田さんの顔がほころぶ。
粂田さんの大学生活の後半はコロナ禍とともにあった
「看護学科の同級生との思い出はたくさんあります。テスト期間は帰りにファミレスに寄ったり、講義がない時間に図書館に行ったりして一緒に勉強していました。みんなが同じ夢を持っていて、看護師の国家試験合格という同じ目標がありますし、実習でも同じグループになった人同士で励まし合ってがんばることができました」
ただし、粂田さんのキャンパスライフは世界情勢に翻弄されている。2年生の終わりが近づいた2019年12月から新型コロナウイルス感染症が世界中で拡大。武蔵野大学は感染防止を図るべく2020年4月から対面授業をとりやめ、全面的にオンライン授業を展開した。粂田さんの大学生活の後半はコロナ禍とともにあった。
「オンライン授業はつらかったです」と打ち明ける。それまで同級生たちと目を見合わせて励まし合ってきたのが、急に一人になったことで孤独感に襲われた。実習も現場ではなくオンラインに切り替えられ、たとえば本当なら生まれたばかりの赤ん坊を実際に見て母性看護を学ぶのに、その体験がないまま保健師になって大丈夫だろうかと不安が募った。
それでも、うつむいてばかりはいられなかった。3年次からは保健師課程も中板育美先生のゼミも始まっていたし、夢は自分で手繰り寄せなければならない。粂田さんは「保健師になるんだ」という強い意志を胸に孤独感を自立心に変えて、前を向いた。コロナ禍の2年間は、実は有意義でもあったと振り返る。
「一人になったことで、講義がない時間もアパートや近所のカフェで集中して看護師国家試験と保健師国家試験、あるいは公務員試験の勉強ができました。本当に保健師になりたいのか、自分とじっくりと向き合う時間を持てたこともよかったと感じています」
ゼミでお世話になった中板先生には全面的にサポートしてもらった。中板先生は公務員試験の小論文対策で手厚く指導してくれたし、川南公代先生とともに繰り返し面接の練習に付き合ってくれた。就職をめざすにあたって、とことん寄り添ってくれる先生たちの存在は本当に心強かった。
看護師国家試験と保健師国家試験、あるいは公務員試験に合格し、2022年3月に卒業
次なる夢は、より広い視野で地域社会に貢献すること
2021年9月3日、第一希望の区から電話があった。保健師としての採用内定を告げられると、うれしくてすぐに両親にLINEでメッセージを送った。
2022年4月から東京都内で保健師を務めている。夢の実現につながった武蔵野大学の看護学部看護学科での4年間は「友だちと励まし合いながら実習を乗り越えたかけがえのない時間」であり、「コロナ禍でつらい状況もありましたが、それを乗り越えられた経験が、今の自信につながっています」と話す。
保健師は保健指導に取り組む存在だ。粂田さんは地域における疾病の予防、健康の維持や増進をめざした活動に励む公衆衛生看護の専門職として充実した日々を送っている。最初の2年間は区役所のなかで主に感染症の対応を行い、3年目の2024年4月からは保健センターで心や体の相談に応じ、乳幼児健診にも関与している。
十代のころ、保健室の先生のような広い心に憧れ、夢を叶えた粂田さんの表情はどこまでも優しい。やりがいを話すとき、表情がより柔らかくなった。
人間としての幅も必要だと感じ、さまざまな本を読むように心がけている
「すべての相談に完璧に応えられているわけではありませんが、悩みを打ち明けられて話したあと、『粂田さんに話を聞いてもらってよかったです』と言われたときはやっぱりうれしいです。『保健師としてこう伝えるべき』といった決めつけではなく、一緒に考えることを大事にしたいと思っています。大切なのはその人自身が最善だと思う道を決めること。自分で決めたことに納得して、豊かな生活を送れるように支援していきたいです」
「もちろん、まだまだ日々、勉強です」と話す粂田さんは、保健師を務め上げるうえでは人間としての幅も必要だと感じ、さまざまな本を読むように心がけている。さらには、先輩方の支援や意見を参考にして、健やかな人生を支える包容力を高めるように意識しているという。
次なる夢は、より広い視野で地域社会に貢献することだ。行政の保健師の特徴を最大限に生かしたいと考えている。粂田さんはなめらかに言う。
「今は個別の支援に力を入れていますが、いろんな人の状況を知って、いろんな選択肢を探して、いずれは個別から見えてきたものを事業につなげたいと考えています」
「いろんな人の状況を知って、いろんな選択肢を探して、いずれは個別から見えてきたものを事業につなげたいと考えています」
※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。
関連リンク
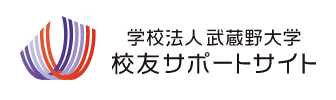












コメントをもっと見る