文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、鷹羽康博
知念美里(ちねん・みさと)さん|株式会社テレパック
東京都八王子市出身。東京都立片倉高等学校では吹奏楽部に所属し、2年次と3年次に全日本吹奏楽コンクールに出場した。2019年3月に武蔵野大学文学部の日本文学文化学科を卒業。在学時にブックカフェのガイドブックをつくった取り組みは思い出の一つだという。2019年4月からテレビ番組や映画の制作などを行う株式会社テレパックに勤め、数々のテレビドラマ制作に携わっている。小学生時代にミュージカルに衝撃を受け、大学時代は何度も劇場に足を運んでいる。好きなドラマは『白い影』。
テレビドラマ『団地のふたり』で初のプロデューサーを務める
NHK BSで放映された『団地のふたり』では自身初のプロデューサーを務めた
二つ大きな仕事をやり遂げた直後に東京の下北沢に現れたのは知念美里さんだ。多くの人が行き交い、不易流行のアートとカルチャーが混じり合って五感を刺激する街が似合うのは、その仕事柄だろう。
「就職活動ではエンターテインメントに関わる会社に幅広くエントリーしました」と言う知念さんは、武蔵野大学文学部の日本文学文化学科を卒業したあと、2019年4月から放送番組や映画の企画、構成、演出、制作などを手がける株式会社テレパックで働く。知念さん自身は主にテレビドラマの制作に携わる。
最近は二つの大仕事をやり切った。小泉今日子さんと小林聡美さんのダブル主演でNHK BSで放映された『団地のふたり』では自身初のプロデューサーを、香取慎吾さんが主役を演じたフジテレビ系木曜劇場『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』ではアシスタントプロデューサーを務めた。
団地で生まれた幼なじみの日常を描いた『団地のふたり』ではギャラクシー賞 2024年10月度月間賞を受賞している。優れたテレビ番組やラジオ番組に贈られるこの賞の受賞は、大きな手応えとなった。知念さんは振り返る。
小学5年生のとき、ミュージカルを観て表現のおもしろさに目覚めた
「もともと原作となる小説があって、『これをドラマ化しないか』と元TBSの八木康夫プロデューサーからお声がけいただいたことでスタートした企画だったんです。NHKの企画募集に応募するために企画書やプロットをつくり、面接などを経て採択していただきました。小泉今日子さんと小林聡美さんをはじめ素晴らしいキャストとスタッフの皆さまのおかげで反響も大きく、この作品をやり遂げたことは大きな自信につながりました」
表現のおもしろさに目覚めたのは小学校5年生のときだ。学校行事で劇団四季の『人間になりたがった猫』を観て心を打たれた。その後、家にいる間はずっとテレビドラマに夢中になる日々を過ごし、ぼんやりとではあったけれど、「いずれはつくり手側に回りたい」という気持ちを抱くようになった。
その思いと武蔵野大学文学部の日本文学文化学科の選択は全く無関係ではない。知念さんは明かす。
「子どものころから本を読むのも作文を書くのも好きだったので、大学では文学部で学びたいと思いました。高校の進路相談室で片っ端から大学のパンフレットを見て武蔵野大学の存在を知り、国語科の担任の先生に話を聞くと『伝統的に文学に強い大学だよ』と教えてもらったんです。家から通える場所でしたし、直感的に『この大学にしよう』と思い、総合型選抜で合格をいただくことができました」
「武蔵野大学の学びは私にとって“実学”の側面もありました」
フィールドワーク的に文学にふれる時間も好きだったという
東京都立片倉高等学校では吹奏楽部に所属し、2度の全日本吹奏楽コンクールを経験している。オーボエを担当していたが音楽はやりきった感覚があり、大学では文学の勉強に没頭する道を選んだ。
実のところ、「文学って何を学ぶんだろう?」と漠然とした思いのまま入学したけれど、武蔵野キャンパスでの学びは掛け値なしに刺激的だった。とりわけ印象に残っているのは土屋忍先生のもとで過ごした3年間だ。2年次にはプレゼミ、3、4年次にはゼミで、「ありとあらゆることを、文学を通して捉えてみたいと思います」と考える土屋先生と近現代文学研究に真摯に向き合った。知念さんが話す。
「私が高校時代まで読んでいたのはエンタメや青春ものの本が多かったんですが、土屋ゼミでは泉鏡花や太宰治といった日本文学界の文豪から、村上春樹さん、山田詠美さん、川上弘美さんといった現代文学界を牽引する作家まで幅広くふれることができました。作品を一つ取り上げてみんなで論じ合うだけでなく、時代背景を知るために作品の舞台となった場所を訪れたり、ある作家にまつわる展示室に足を運んだり、今になって思えば、武蔵野大学の学びは私にとって“実学”の側面もありました」
「ありとあらゆることを、文学を通して捉えてみたい」という土屋先生との時間はとことん楽しかった。3年生のとき、文化祭にあたる摩耶祭では文学と音楽にまつわるカフェを出店したのもいい思い出だ。知念さんは得意のオーボエで参加し、村上春樹がタイトルに採用したビートルズの『ノルウェイの森』や、『驟雨』で芥川賞を受賞した吉行淳之介の母の生涯を描いたテレビドラマ『あぐり』のテーマ曲などを数名で演奏した。単に文学作品を読み解くだけでなく、音楽しかり、ドラマや映画と絡めて文学を追究する楽しさを土屋先生が教えてくれた。
「ありとあらゆることを、文学を通して捉えてみたい」という土屋先生(左から2人目)との時間は楽しかった。知念さんは右から2人目
卒業論文では青木和雄による児童書の『ハッピーバースデー』を取り上げた。母から精神的虐待を受けながらも母からの愛を求める「あすか」を軸に展開する作品には中学生のときに出合っていた。アニメ映画化やテレビドラマ化もされており、「児童虐待を描く文学の在り方—青木和雄『ハッピーバースデー』にみる世代間連鎖の防止」と題された卒業論文ではテレビドラマなどと比較しながら、虐待を受けていた過去を持つ親が自身の子どもに対して虐待してしまう「世代間連鎖」を防ぐ役割を文学作品が担うことはできるのかという点にフォーカスを絞り論じた。
「児童福祉に通ずるような作品をいつかは手がけたい」
子ども向けのブックイベント「ワクワクことばのひみつきち」を切り盛りしたメンバーたちと。前列左から3人目が知念さん
2018年12月24日、竣工したばかりのむさし野文学館には子どもたちの元気な声があふれていた。
その日行われていた子ども向けのブックイベント「ワクワクことばのひみつきち」を先頭に立って企画し、準備したのが知念さんだ。むさしの文学館が入っている紅雲台のすべてを使って、読み聞かせをしたり、工作をしたり、本の交換会を行ったり、子どもたちの笑顔が広がる空間をつくりたかったという。
「卒業論文で扱った『ハッピーバースデー』もそうですし、『Mother』というテレビドラマもそうなんですが、十代のころに食い入るように観た作品の多くが児童虐待を描いているんですよね。その影響からか児童福祉にずっと関心があったんです。ですから、『ワクワクことばのひみつきち』の入場料と会場で集まった募金はすべて、子ども虐待防止を訴える『オレンジリボン運動』に寄付しました」
大学生活の最後に力を入れた児童虐待防止活動からは、テレビの世界に入った今も目を背けることができない。「児童福祉に通ずるような作品をいつかはやりたいとずっと思っています」と話す。いくつか内定をもらった制作会社からテレパックを選んだのは、ドラマ制作の実績が豊富だったからだ。大好きなドラマを通じて子どもたちの未来を照らすような作品をいずれは発信したいと考えている。
『団地のふたり』で初プロデューサーを務め、小さくない自信をつかんだ知念さんにとって、この先の未来に通じるのは武蔵野大学で過ごした4年間だ。テレパックに入社し仕事を進めるなかでほどなく思ったのは「これって土屋ゼミの延長だな」ということだった。
「台本やプロットを前に、まずじっくり読んだり、ストーリーの背景を考えたり、登場人物の心境を議論し合ったり、なぜそういう展開なのかを読み取ったり、ドラマ制作の仕事は土屋ゼミから連なっています。『プロデューサーの役割はゼロから1を生み出すこと』とよく言われるのですが、そこは大変でもありながら、この仕事の醍醐味だと思うので、その楽しさを忘れずにいずれは児童福祉に通じるドラマを手がけたいです」
「大学時代からずっと楽しいことをやっているなと思います」と話す知念さんは、テレビの世界で夢を追いかけていく。
「大学時代からずっと楽しいことをやっているなと思います」
※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。
関連リンク
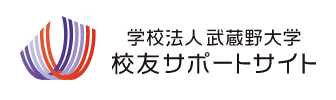













コメントをもっと見る